「そもそもAWSってなに?」
「なんだか難しそう、、、」
「AWSってどうやって勉強すればいいの?」
そんな風に感じていませんか?
この記事では、ITの知識に自信がない方でもAWSの全体像をつかめるように、仕組みやメリット、私たちの生活との関わりまで、イメージでわかりやすく解説します。
読み終わる頃には、「なるほど、AWSってそういうことか!」とスッキリしているはずです。

なおと
AWSフリーランスエンジニア
当ブログ「なおナビ」運営者の、なおとです。
▽略歴
- IT完全未経験からAWSエンジニアに転職
- AWSエンジニアに転職して年収400万円アップ
- フリーランスとして独立(2025.11~)
このブログでは、AWSエンジニアやフリーランスを目指す「あなた」の背中を押す情報を発信しています💡
そもそもAWSって何?
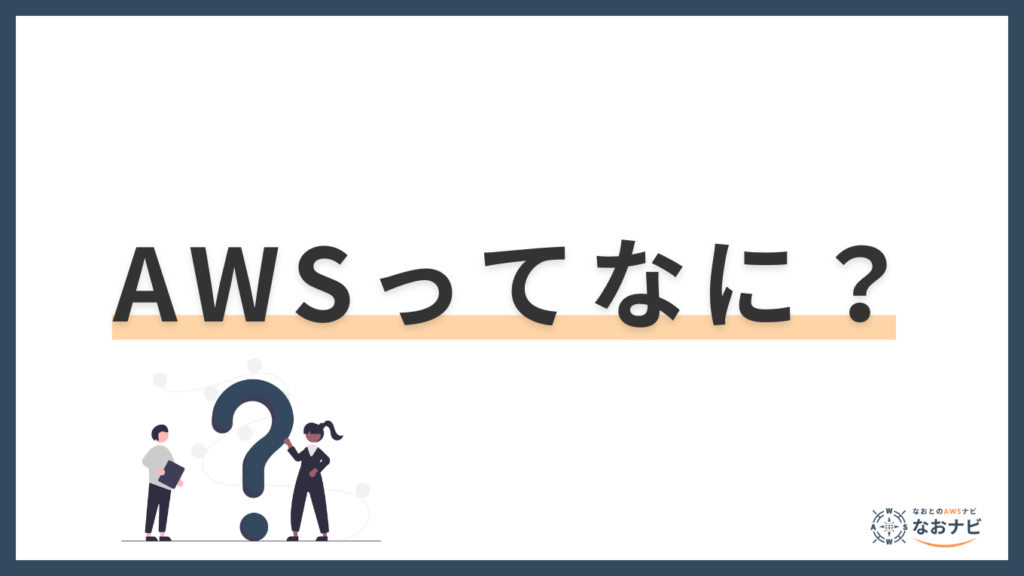
AWS(エー・ダブリュー・エス)とは、「Amazon Web Services」の略です。
その名の通り、通販サイトで有名なAmazonが提供しています。
AWSには以下の特徴があります。
インターネット経由で使える、ITのレンタルサービス
一言でいうと、「インターネット経由で使える、ITの部品レンタルサービス」です。
昔はWebサイトを作ったり、会社のシステムを動かしたりするには、サーバーと呼ばれるコンピューターなどの「ハコ(物理的な機械)」を自分で購入し、社内に設置して管理する必要がありました。
これを例えるなら、自宅で使う電気を大きな自家発電機を買ってきて自分でまかなうようなものです。
発電機の購入費もかかりますし、置き場所の確保、燃料の補給、故障した時の修理など、すべて自分でやらなければならず、非常に大変です。
クラウドコンピューティング
一方、AWSをはじめとする「クラウドコンピューティング」は、電力会社から電気を買うのと同じです。
クラウドコンピューティングとは
インターネット経由でサーバーやストレージ、ソフトウェアなどのコンピューティングリソースを月額課金で利用できる形式のことです。
私たちは、自分で発電機を持たなくても、コンセントにプラグを差すだけで電気を使えますよね。そして、使った分だけ電気代を支払います。
AWSは、この「電力会社」の役割をITの世界で担ってくれます。
Amazonが世界中に用意した巨大なデータセンター(発電所のようなもの)にあるサーバーやデータベースといったITの部品を、私たちはインターネット(送電線のようなもの)を通じて、必要な時に必要な分だけ借りて使うことができるのです。
AWSを使う4つのメリット
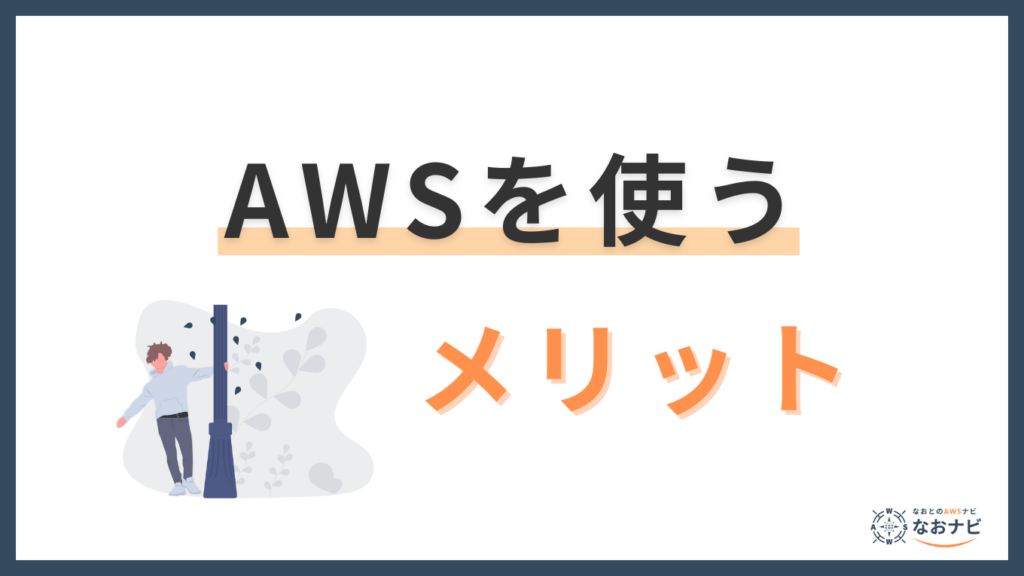
自家発電(自社サーバー)ではなく、AWS(電力会社)を選ぶと、以下の4つのメリットがあります。
以下のメリットはAWSに限らず、クラウドコンピューティングならではのメリットとも同じです。
① 初期費用が安い(ほぼゼロ!)
サーバーなどを自前で用意する場合、最初に数百万円といった大きな投資が必要です。
しかしAWSなら、アカウント作成は無料で、使った分だけの「従量課金制」。
まるで水道光熱費のようです。
ブログを立ち上げたい、新しいサービスを試したいと思った時に、気軽に始められます。
② 必要な量をピッタリ使える(柔軟なサイズ変更)
もしあなたのWebサイトがテレビで紹介され、アクセスが急に100倍になったらどうでしょう?
自前のサーバーでは処理が追いつかず、サイトが見られなくなってしまいます(サーバーダウン)。
AWSなら、お店のレジが混んできたら、すぐに応援スタッフを呼んでレジを増やすように、サーバーの能力(処理能力)を数クリックで増強できます。
もちろん、アクセスが落ち着けば元に戻して、余計な費用を抑えることも可能です。
③ 面倒な管理から解放される
自前のサーバーは、24時間365日、安定して動かし続けなければなりません。
ホコリが溜まらないように掃除したり、故障したら部品を交換したり、停電対策をしたり…といった管理はとても大変です。
AWSを使えば、そうした物理的な機器の管理やメンテナンスは、すべてAmazonの専門家がやってくれます。
私たちはサービス開発など、本当にやりたいことに集中できるのです。
④ とにかく頑丈で安全(高いセキュリティ)
「大事なデータをAmazonに預けて大丈夫?」と心配になるかもしれません。
しかし、AWSのセキュリティは世界最高水準です。
金融機関や政府機関など、極めて高いセキュリティが求められる組織も利用しています。
Amazonが自社の巨大なネット通販事業で培ってきた、鉄壁のセキュリティ技術をそのまま利用できるので、とても安心です。
もちろん弱点も…【デメリット】
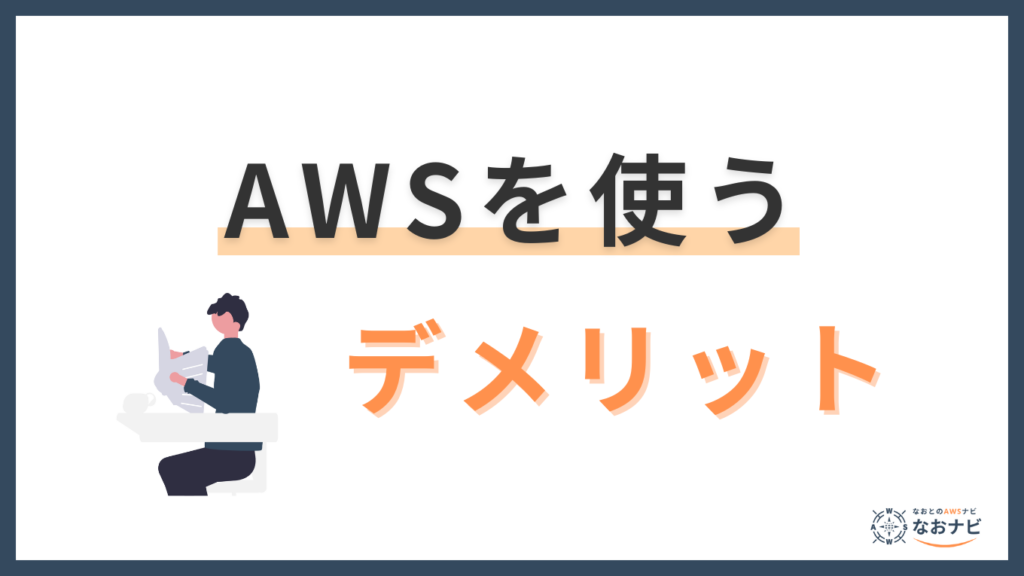
良いことずくめに見えるAWSですが、注意点もあります。
専門知識が必要
AWSには200以上のサービス(ITの部品)があります。
便利な反面、「この目的には、どの部品をどう組み合わせれば最適か?」を判断するには、ある程度の知識が必要です。
この役割を担っているのが、「AWSエンジニア」です。
AWSエンジニアについては下記の「AWSの仕事内容」の記事で詳しく解説しています。
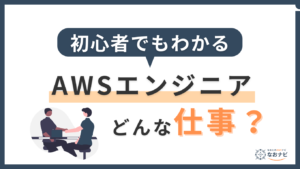
コスト管理が少し大変
使った分だけ支払う従常課金制はメリットですが、電気をつけっぱなしにすると電気代が高くなりますよね?
それと同じで、サービスの利用状況をきちんと管理しないと、想定外の高額請求につながる可能性もあります。
結局、AWSで何ができるの?【身近な活用例】
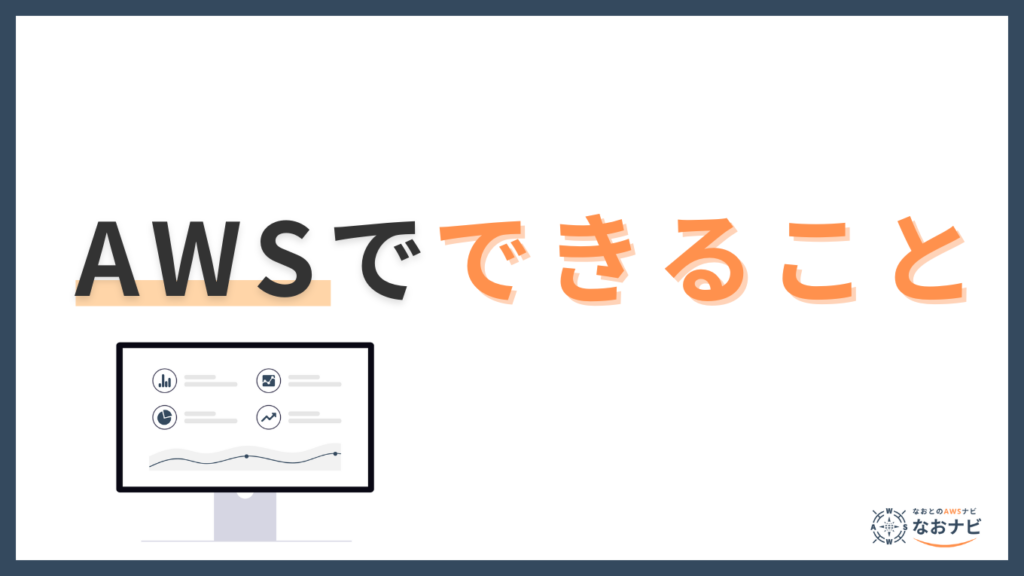
実は、私たちの多くが毎日気づかないうちにAWSのサービスに触れています。
例えば
- 動画配信サービス
- Netflixなどのサービスは、膨大な映画やドラマのデータを保存し、世界中のユーザーにスムーズに配信するためにAWSを活用しています。
- 音楽配信サービス
- Spotifyなども、膨大な楽曲データやプレイリストの管理にAWSを使っています。
- スマホアプリやオンラインゲーム
- 多くのスマホゲームのデータ保存や、Nintendo Switchのオンライン対戦の裏側でもAWSが活躍しています。
- Webサイト・ブログ
- 企業の公式サイトから個人のブログまで、世界中のWebサイトがAWS上で公開されています。
このように、AWSは現代のインターネットサービスを支える、なくてはならない「土台」のような存在なのです。
AWSを学び始めるには?
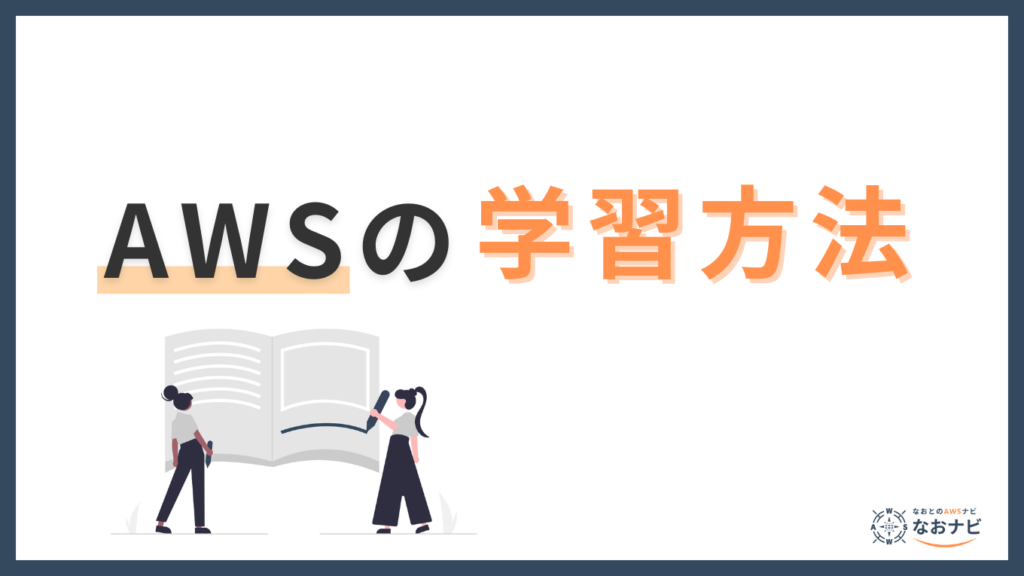
「ちょっと面白そうかも!」
そう感じた方へ朗報です。
AWSは、初心者でも学習を始めやすい環境が整っているので学習が非常に進めやすいです。
AWSの学習方法について代表的なものをまとめました。
参考書で学ぶ
まず2つの参考書を紹介します。
両方買う必要はないので自分に何となく合いそうな方を選べばOKです。
参考書での学習が苦手な人はオンライン学習サイト⇩で学ぶことをオススメします。
①図解即戦力 アマゾン ウェブ サービスの仕組みと技術がこの1冊でしっかりわかる教科書
AWS(アマゾン ウェブ サービス)の初心者解説書です。
AWSの各サービスの特徴をクラウドやネットワークの基礎から解説している本です。
今までのAWS解説書では用語が分からず難しかったという人も、この本なら最後まで読むことが出来ると思います!
②AWSの基本・仕組み・重要用語が全部わかる教科書 (見るだけ図解)
こちらも初心者におすすな書籍。
図解がたくさん入っているので、文字だけだと頭に入ってこない人にも視覚的にわかりやすい書籍になっていておすすめです!
AWS無料利用枠を試す
1番のおすすめは、実際に触ってみることです。
AWSには、一部のサービスを一定期間または一定量まで無料で使える「無料利用枠」が用意されています。
これを使えば、お金をかけずにAWSを体験できます。
オンライン学習サイトで学ぶ
Udemyなどのサイトには、初心者向けの動画講座が豊富にあります。
動画を見ながら一緒に手を動かすことで、効率的に学習を進められます。
1つ前で紹介したAWSの無料利用枠を利用することで、お金をかけることなく学習が可能です。
入門資格を目指す
「AWS 認定クラウドプラクティショナー」という資格は、AWSの基本的な知識を証明する入門者向けの資格です。
エンジニアだけでなく、営業職や企画職の方にも人気で、学習の目標にするのにピッタリです。
AWSエンジニアを目指したい方は「AWS 認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト(AWS SAA)」から学ぶことをオススメします。
現場や実務ではAWS SAAレベルの知識が必要となるためです。
AWS SAAに合格するための、学習方法や必要な勉強時間については下記の「AWS SAAの合格体験記」で詳しく解説しています。
AWS SAAを取得したい!と思っている方はぜひこちらもご覧ください。
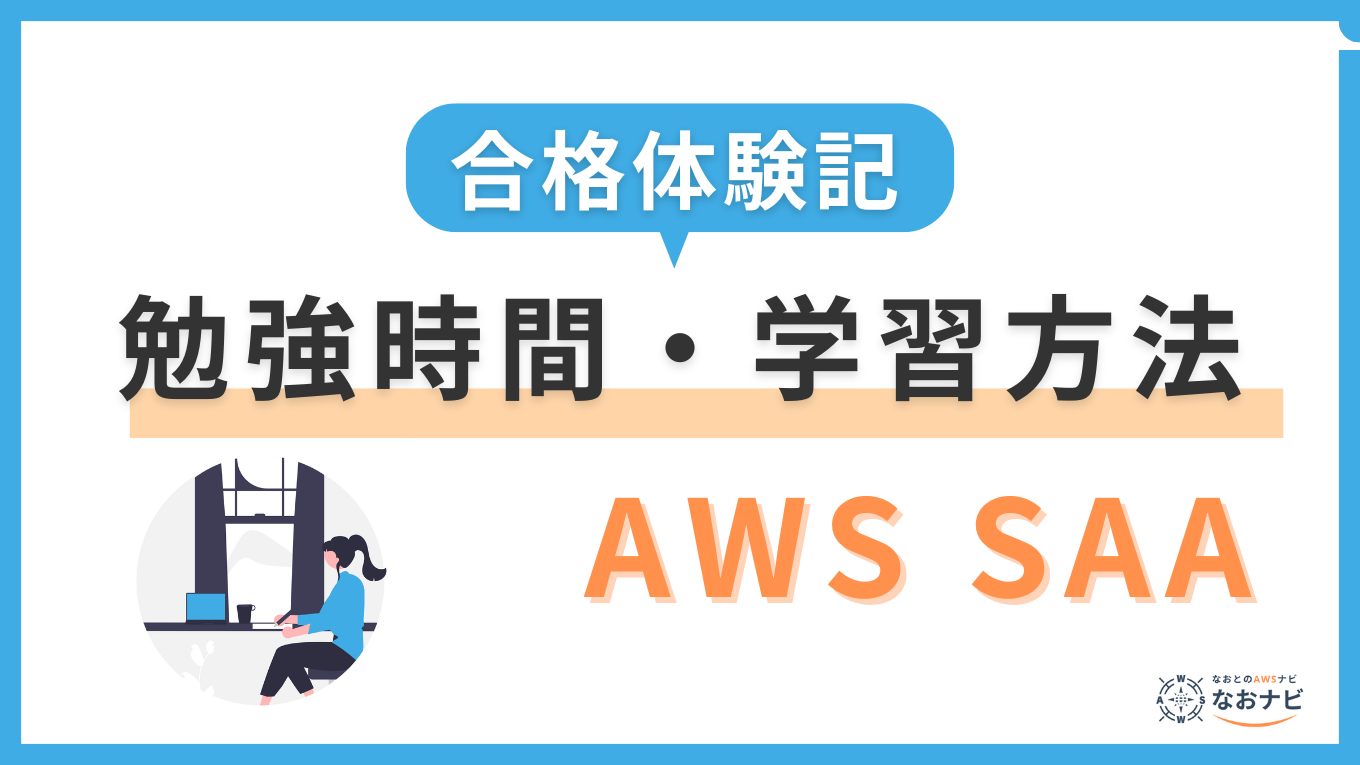
また、AWSエンジニアになるための3ステップは以下の記事でさらに詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
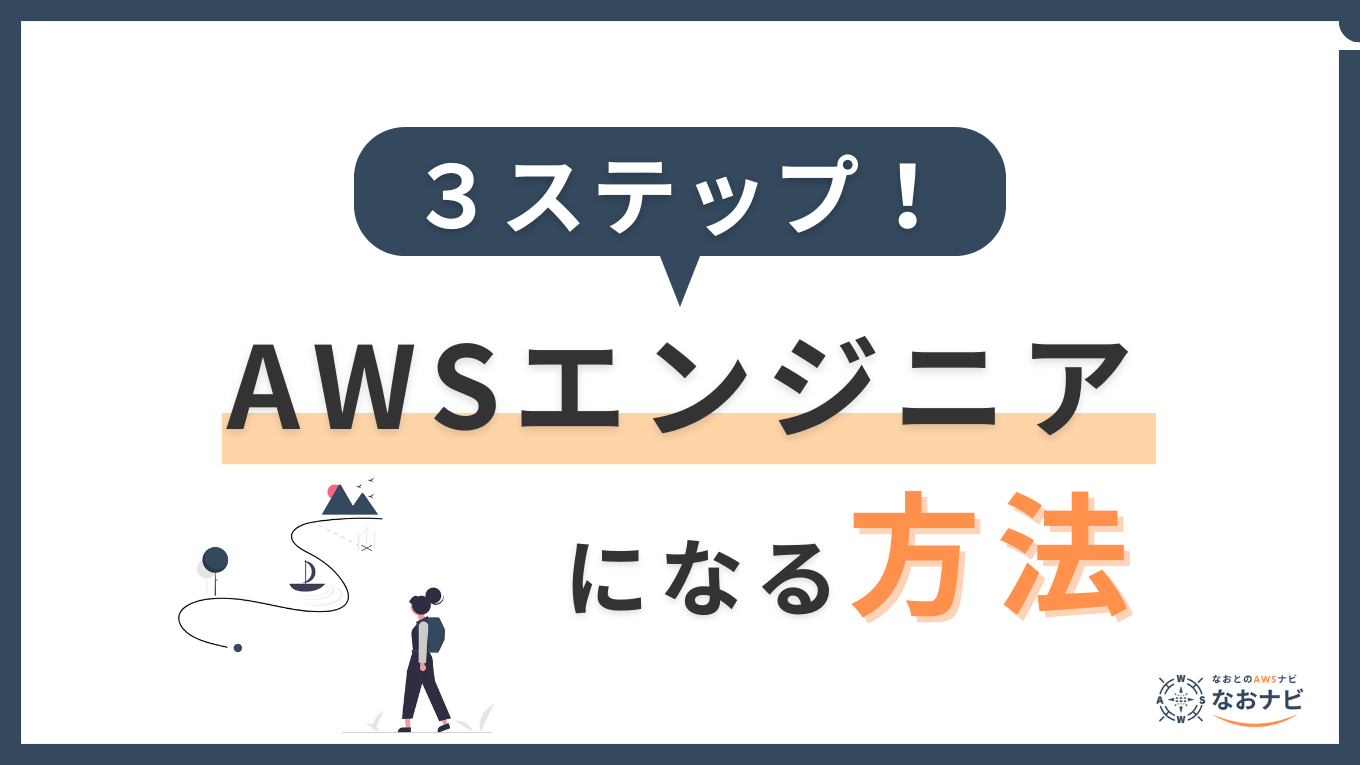
まとめ

この記事では、AWSを「インターネット経由で使える、ITの部品レンタルサービス」とご紹介しました。
そのメリットは、
- 低コストで始められる
- 状況に応じて柔軟に規模を変えられる
- 面倒な機器管理が不要
- 非常に安全
という点にあります。
最初は少し難しく感じるかもしれませんが、世の中にも広く普及している便利なサービスです。
まずは無料利用枠でアカウントを作り、どんなサービスがあるか公式サイトを眺めてみるだけでも、きっと新しい発見があるはずです。
ぜひ試してみて下さい!
本サイト「なおナビ」では、AWSエンジニアにまつわる情報を発信しています。
- AWSエンジニアについて知りたい!
- AWSエンジニアになる方法が知りたい!
- ぶっちゃけAWSエンジニアって稼げるの?
こんな疑問を持っている方はぜひ他の記事も読んで、AWSエンジニアについて知ってもらえたら嬉しいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
今回はAWSについて解説しました。
AWSの全体像について、何となくつかめたでしょうか?
記事を読むだけで理解するのは難しいと思いますが、AWSについてさらに興味を持つきっかけになったら嬉しいです。

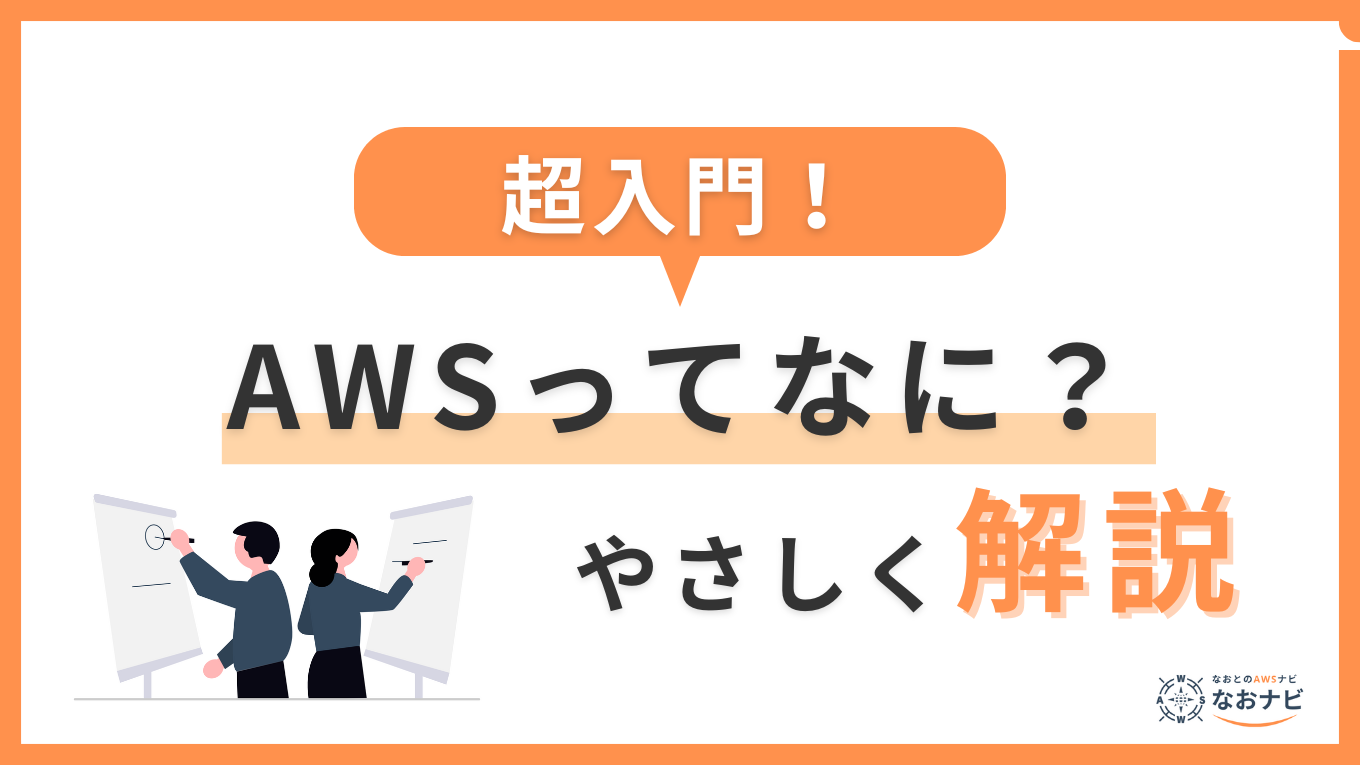

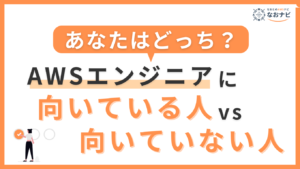
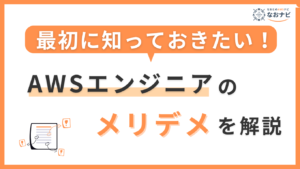
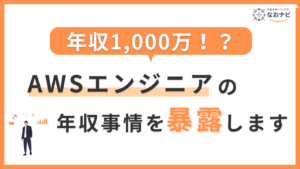
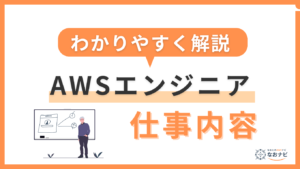
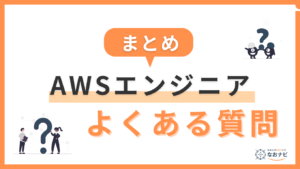
コメント